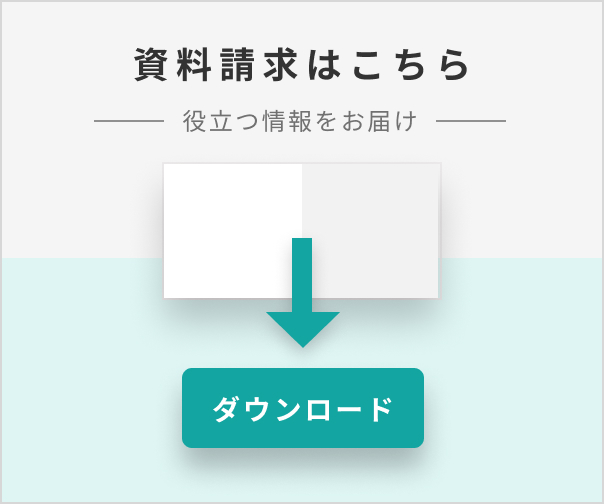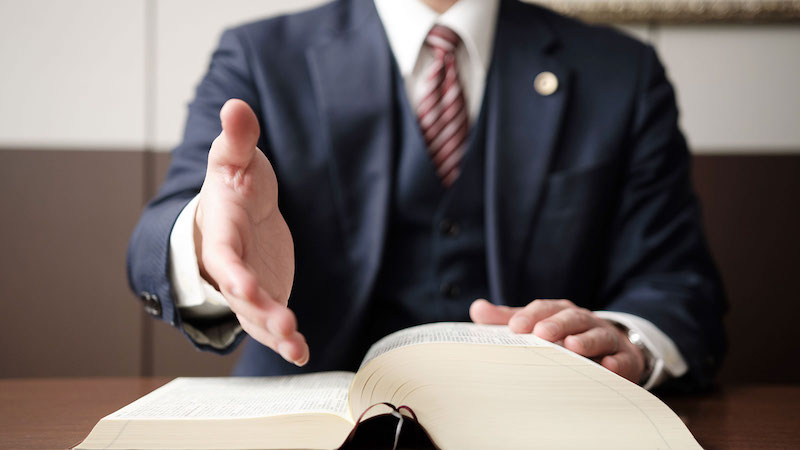構造化面接とは?質問例やメリット、注意点をまとめて解説
優秀な人材を継続的に採用することは全ての企業において最も重要な命題の一つです。
面接でありがちなのは面接官の主観によって候補者の評価が大きく変わり、入社後にミスマッチになってしまったり、経験の浅い社員が面接を担当する場合、評価の基準が分からず合否を判断できないケースです。そのような状況を回避するためには、客観的に候補者を評価する手法である「構造化面接」がおすすめです。
この記事では、構造化面接の質問例やメリット、実施する際の注意点について詳しく解説します。
目次
採用における面接官の役割
構造化面接とは
構造化面接のメリット
構造化面接を実施する4ステップ
構造化面接の質問例
構造化面接を実施する際の注意点と対策
まとめ

back check magazine編集部
江田有梨亜
株式会社ROXX back check事業部にてマーケティング業務に携わる。